Alephant
牛が象に勝てるわけないだろ
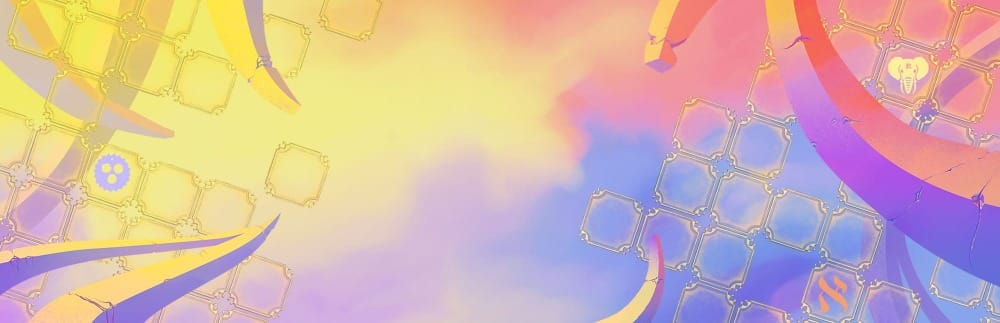
Niqqudを押してAlephと連結し、連結されたAlephを踏むと音が鳴る。すべてのAlephで音を鳴らすとクリア。音を鳴らすと特殊な効果が表れ、Alephと連結されたNiqqudにより効果が異なる。KamatzはすべてのNiqqudが音の鳴ったAlephに向く。Segolは直線上に存在する別のAlephにワープする。Hiriqは直線上の他のNiqqudおよびAlephを1マス引き寄せる。
こうして書き出すとそこまで複雑なルールには見えない(固有名詞の聞きなれなさはすごいけど)。ステージはどれも盤面が狭く、最小限の構成になっている。それでもすぐに手詰まりになってしまう。手詰まりとなる状況を一つずつ避けていくと、動かせる場所がほとんどないことに気づく。それなのに答えがわからない。なにか見落としているんじゃないかと思って別の選択肢を試すもやはり手詰まりになる。
この見落としが発生する原因は、盤面が回復不可能な状態かどうかの判断が難しい点にあるような気がした。Alephによる音の効果で、シンプルな倉庫番では回復不可能な状態から復帰できることもある一方で、逆に詰み状況になってしまうこともある。
自分が最初にガッツリ詰まったステージ「ALEPH - L」では、Alephと重なるようにNiqqudを並べて押すと、Alephを踏まずにNiqqudを移動できると気づく必要がある。他の高難度ステージでも「音を鳴らさずにAlephを移動または通過する方法」に関する知識が必要になることが多い。
特にKamatzの音の効果は盤面全体に影響を与える。つまりプレイヤーの選択肢に起因して、非対称な相手プレイヤーが盤面を操作していると言えるのではないか。単純な倉庫番に「相手側」の概念が生まれて、組み合わせゲームの複雑さが追加されているのかも。
出来る限り音を鳴らさず、相手側に手番を与えないようにプレイしたいが、時には相手を動かすことも必要になる。一人用の倉庫番パズルゲームなのに対戦ゲームのような緊張感があった。
なんらかの音を発して相手と手番を交代するのは、パズルゲームの仕組みで対話を表現しているように見えた。「puzzle game about language」と自称していることから、他にも言語に関係する発想がゲームとしての仕掛けのなかに隠れているかも。
プレイヤーの選択によって、盤面の状況が変化する要素のわかりやすい実装だと、自分が思い出せる中では『Headlong Hunt』のオレンジの生物、『パクレット』のウサギ、『RIKO』のモンスター、『BABA』のMOVEなどがある。このような一見して動きのある要素と違い、Alephがこの特性を持っていることが、意外性をもたらしているのかもしれない。自分がやった中ですごく近いものだと『Stig』の色マスがある。『Stig』の色マスはゴール条件そのものを操作するので、盤面全体よりも上位の概念なのかも。
このゲームの「音」の効果や、『Stig』の色マスのように、パズルにおいて、盤面全体やゴール条件そのものに影響を与える要素がなんと呼ばれているのかについてちゃんと調べると楽しいかもしれない。いつかやれたらやります。
シンプルな倉庫番の詰み状況について調べていたら、倉庫番がPSPACE完全問題だという証明があるらしい[1], [2]。倉庫番でチューリングマシンをエミュレートできるので、PSPACE困難なことが証明できるらしい。正直あんまちゃんと証明は読んでないけど、倉庫番における詰み状況や一方通行の状況について図とともに紹介されているので面白かった。
倉庫番のバリエーションとして、引っ張る動きがある場合についても研究が進んでいるらしい[3]。なんかもう全部解析されてたりしない?でも最新のLLMでも『BABA IS YOU』はまだ全然解けなかったりするらしいし[4]、計算量で問題が一気に解決するようなもんでもないのかも。



