Frontiers of the Mind
CDに脳みそプリントされてるじゃん
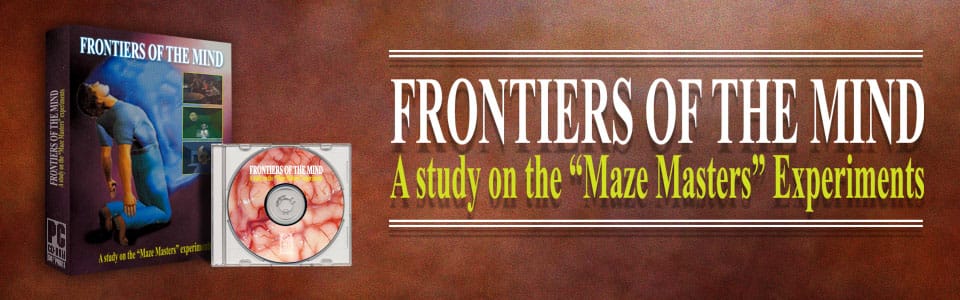
えっとつまり、イギリスで放送されていた子供向けゲームショー『Knightmare』をモチーフにした架空の番組『Maze Masters』の舞台裏や設定資料をまとめた、架空のCD-ROMの内容を確認しているという設定で、その番組の制作過程では、プロデューサーの奇妙な陰謀が働いており、その影響(?)でCD-ROM内でも怪奇現象のようなものが発生している……ということ?
ゲーム中に登場する怪異や人物は、そこまで独特で奇抜な発想のものではなく、すべての要素が作中で回収されるわけでもない。結末もどこか曖昧で、解釈の幅が広いというほどでもないため、よくある考察系ホラーと言われそうではある(誰によって?)。しかし、このゲームの特徴はそこではなく、現実のテレビ番組をモチーフにした具体的で詳細な放送事故や裏話として、怪奇現象が表現されている点にあるのかなと思った。
プレイ中、90年代の子供向けゲームショーとして、なんとなく『天才てれびくん』[1]を思い浮かべた。ただ、そもそも自分は熱心な視聴者ではなかったので、具体的に誰が出演していたか、どんな企画があったかなどはほとんど覚えていない。ただ、ぼんやりとした画面の雰囲気だけがかろうじて浮かんでくる感覚があり、それはある意味、ゲーム中に登場する低解像度のスクリーンショットと同じだったのかもしれない。
当時の自分は、まだ自我が芽生えたばかりの子どもで、恥をかくことを何よりも恐れていた。番組内で同年代の子供たちが奇妙なことをさせられたり、明らかなミスを犯したりする様子が地上波で放送されるのを、まるで自分が笑われているかのように感じて見ていられなかった。実際には、子供にとっては恥を恐れず行動できる環境こそが大切なのだと気づいたのは、だいぶ後になってからだったのだけれど。
気持ちよく自分語りしてしまった[2]が、『天才てれびくん』と『Maze Masters(Knightmare)』は、放送地域こそ違えど、同年代向けの子供番組としてなんとなく雰囲気が似ている。だから、ちょうどイギリスで『Knightmare』を見ていた人と同じ種類のノスタルジーのツボを押されたように感じたのかもしれない。
子供向けに限らず、90年代のテレビ番組は今と比べると大雑把で、どこか怪しげな雰囲気があった。それがコズミックホラー(?)的な怪異と相性が良いのは、おそらくこのゲームが初めて発見したことではないだろうけど、ここまで具体的かつ詳細に表現されたものは、自分の管見では他に知らない。
さらに、このゲームでは90年代のキッズ向けゲームショーをテーマにしているが、単なるノスタルジックな舞台装置にとどまらず、2000年代初頭の教育用PCソフトの形式で表現され、その裏側にある番組制作者たちの青春時代——70~80年代のニューエイジ運動[3]にも触れている。番組プロデューサー「J」がのさばった時代の厚みを感じられることで、なんか、いいものを読んだなという気持ちになった。
プレイ後に実際の『Knightmare』について調べ、2013年に当時のキャストやスタッフが集まって制作されたYouTube上の復刻版を見た。元の番組を一度も見たことがないのに、このゲームで知った小道具や仕掛け、キャラクターが次々と登場し、まるで仮想的なノスタルジーを植え付けられたような、不思議な感覚に陥った。



