霊言
「どうしましょう、博士、白い部屋でイーロン・マスクと二人きりになってお互いを理解しろと言われても、できる気がしません。」
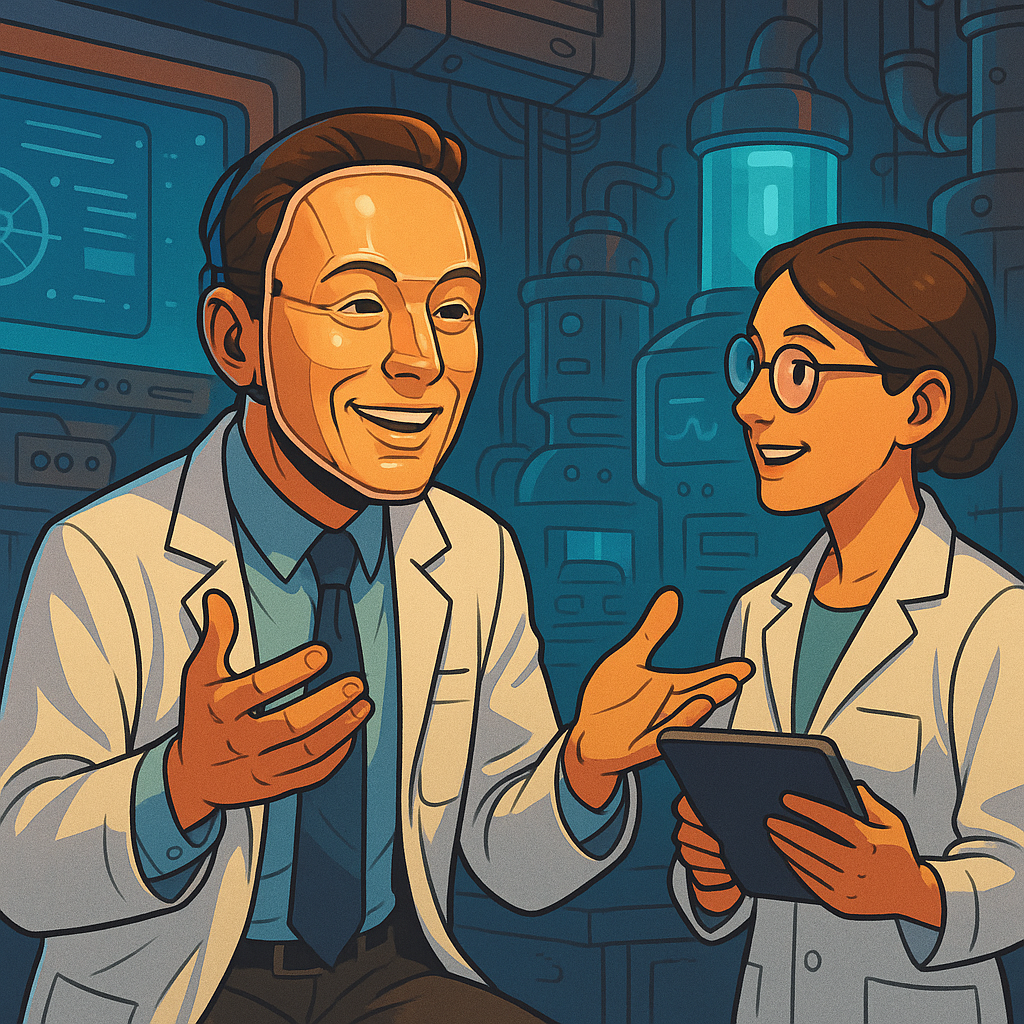
「どうしましょう、博士、白い部屋でイーロン・マスクと二人きりになってお互いを理解しろと言われても、できる気がしません。」
「なるほど、『イーロン・マスクと分かり合うまで出られない部屋』か……たしかに難問じゃな。」
「試しに、博士、イーロン・マスクをやってみてくれませんか?」
「ふむ、少し荷は重いがやってみよう。」
「ありがとうございます。イーロン・マスクさん。とはいえどこから始めようか……まずイーロン・マスクは私のことを知らないはずなので、私がイーロン・マスクについて思っていることを率直に述べますと、正直なんか嫌いです。でも、なぜ嫌いなのかを掴みかねているんです。単純に、言ってることややってることはほんとしょうもないのに、なんか金持ってるおかげでバカなシンパが存在するのが気に食わないのかもしれません。あるいは、もっと深い、人生に対する考え方や思想の違いがあるのかも……これをはっきりさせるためにもイーロン・マスクさんがこれまでやってきたことに対して、どういう意図とか、考えを持っていたか説明していただけないでしょうか?まず、ツイッターを買収したのはなぜですか?」
「まあ、やっぱりメディアだからね、ツイッターは。金持ちといえばメディアを持ってるイメージがあるから、そういうのに憧れるんだよね。ほら、市民ケーンでも新聞王が主人公だったろ?」
「市民ケーンをみて新聞王に憧れたんですか?あれは最終結構新聞王が悲しい感じになりますが、あれを見て憧れるなんてことがありますかね?何か隠していませんか?」
「そうだね、さらに有り体に言うと買えるから買っちゃおうという感じかな。やっぱりぼくは正直言って結構金持ってるし。例えるなら、子供の時はブタメンを買うのにも結構躊躇するじゃない?やっぱ100円とかしか持ってないから。でも大人になると全然1000円とか普通に使えるから、ブタメンとか躊躇なくいつでも買えるでしょ?そういうことだよ。」
「ブタメンですか?でもブタメンは常に正解なので(だって美味しいから)子供でも躊躇なく買うと思いますが……」
「オーケー、ブタメンで例えたのが悪かったね。じゃああれだ、『タラタラしてんじゃねーよ』だ。『タラタラしてんじゃねーよ』は大人になった今なら、あれくらいの刺激がないと食べた気しないから、だいぶ良いけど、子供は辛いの苦手だからちょっとどうかな〜ってなるだろ?つまり、『タラタラしてんじゃねーよ』ってことだよ。」
「どういうことですか?あのパッケージのヴォーカリストがあなたということですか?」
「いや、そういうことじゃない。ぼくは市民ケーンだ。そしてあのヴォーカリストがツイッターということになる。」
「ちょっと理解できません。そもそもよっちゃんイカではだめなんですか?」
「よっちゃんイカはイカだから、スプラトゥーンになっちゃうだろ?だから違う。ツイッターじゃない。」
「タラタラしてんじゃねーよも魚介類なので、スプラトゥーンなんじゃないですか?」
「あれ魚貝類なの?具体的に何?」
「タラじゃないんですか?」
「あれってその『タラ』なの?」
「はい。」
「なるほど。まあ実際それはどっちでもいいんだよ。結局はお金が余ってるから買えちゃったってことだよ。そういうこと。そもそもテスラもそうだし。なんか自動車って金持ちのイメージだから。言っても結構年だから、古いタイプの金持ち像持っているんだよ。」
「実際ツイッターはそんなに買いたいわけではなかったということでしょうか?」
「まあそういうことだね。これ、オフレコだけどね(笑)。」
「……」
「つまりは、人生でやりたいことリストみたいなのはみんな持ってるだろ?そのなかでとりあえずやれそうなことをやってみてるってことさ。あんまりしっかり優先度をつけずにしてるんだよ。そういうのって、考え方によるけど、しっかりやろうとするとドツボにはまったりするじゃない?まあ、これで伝わったかな?」
「なるほど……なんとなくわかってきた気がします。つまり、ツイッターはブタメンではなくよっちゃんイカでありタラタラしてんじゃねーよだということ(ただしスプラトゥーンではない)。金持ちはメディアと乗り物を欲しがるということ。どれだけ金持ちであっても、人生はやりたいことをすべてやるには短すぎるということ。どれも合点はいきます。ただ、私があなたほど金を持っていたとしても同じことをしているとは思えません。なんか態度が図々しいですし、自分は人よりも金を持っているという自覚がある上でちょっと変なこと言ったり、イタいことしたりするのって、なんかそれって、自分はそれでも許されるんだということを確認してるみたいで……意図は図りかねますが、もしそれが、自分が安全な環境にいるかどうかを判断しようとしてしているんだとしたら、ちょっと子供っぽくて恥ずかしくないですか?」
「まあ、実際不安ではあるからね。ぼくレベルの金持ちになると、同じ境遇の人間ってほとんどいないからね。街を歩いていても、みんな僕の持ってる資産の1000分の1すら持ってないんだって思うと、常に狙われているんじゃないかと勘繰ってしまうよね。でも、ぼくの方法が子供っぽいんだとしても自分は安全かどうか確認する正しい方法ってあるのかな?少なくともぼくが金を持っているからと言う理由だけで一目置いてくれる連中がいるということは、ぼくの立場は客観的に見て安定している証拠になるんじゃないかな?そしてそういう連中をあぶり出すには割と効果的な方法だと思けどね。」
「でも、そういう連中は信頼できないんじゃないですか?」
「信頼はできないさ(笑)。でも、そうじゃない連中なら信頼できるってわけでもない。逆に、金をチラつかせればカラスも白いって言う奴らのほうが、ぼくにとっては安全なんだ。」
「金玉をチラつかせるですって?」
「え?」
「お金を払って金玉をチラつかせてカラスが白くなるまで射精するとおっしゃいましたか?」
「なんだって?金玉カラスの写生大会を開いた覚えはないが……でも、カラスの金玉を上手に描ける人間は信頼できる……それだ!早速開催だ!」
そして大会当日集まったメンバーは……
- キング・K・ルール
- ホリ(ものまね芸人)
- だいたひかる
- 土屋太鳳
- マー坊(ヤン坊マー坊)
以上5名。
イーロン・マスクが学校のグラウンドとかにある校長先生が立って喋るやつにちょっと駆け足で登ってからおもむろに喋りだす。「よーし!今日集まってもらったのはほかでもない!これから、みんなには俺様に最も似合う毛糸のパンツを編んでもらう!」
だいたひかるがすかさずツッコむ。「写生大会と聞いていたのは、私だけでしょうか」
キング・K・ルールは腹を叩いて笑っている。ホリ、土屋太鳳、マー坊の3名は鉄砲水に流されて死んだ。イーロン・マスクはだいたひかるの方を見て、ハッとしたような顔をしている。何かに気づいたようだ。(俺に足りなかったのは『ツッコミ』だったのかもしれない。俺はこれまでたった一人でボケ続けていた、まさしく『孤高のボケマシーンと言われているのはこの男〜!』だったのかもしれない……)
イーロン・マスクの股間のブラストマティック砲もビンビンになっていた。(やばい!どうしてこんなときに……)イーロンは慌てて壇上から降り、その瞬間がまさに、あのおぞましい殺戮ショーの幕開けとなるとは、このときはだれも予想できなかった。
