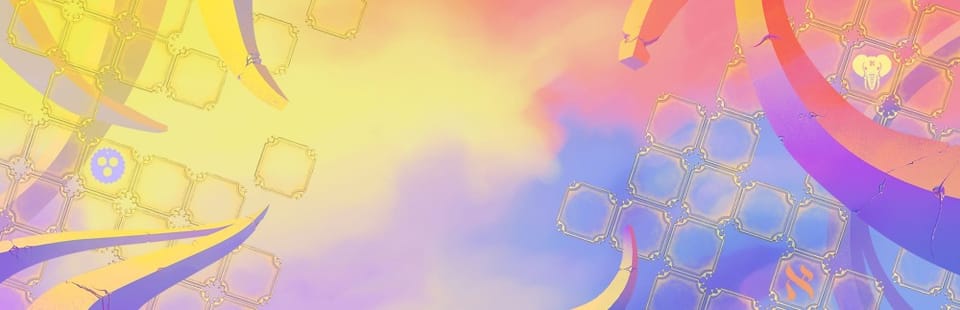NORCO
結局 Stone は何だったの?

巨大企業による事故の隠蔽や公害問題、仮想通過目当てにアプリの指示に従って意図の不明な依頼をこなす闇バイトのような現実的な社会問題の延長から、奇妙な幻覚のような呪術的なモチーフまで、それらが Norco というどこか馴染み深い地元を思い出させる雰囲気のなかでシームレスにつながっていて、ちゃんと目的に向かってゲーム中の課題をこなしているはずなのにどんどん迷子になっているような気分だった。
行方不明の弟と、死んだ母親の足跡を探すことが目的だが、基本的に目の前の手がかりを追っていくのに精いっぱいなので、話も直線的ではなく行き当たりばったり、その場その場での対処の連続で、そこにさらに荒唐無稽なジョークまで挟まれるので終始混乱しっぱなしだった。
ただ、これまで出てきた関連する情報を簡潔にまとめてくれる Mind-map の機能により割と話に振り落とされることはなかったし、これが少しずつ開放されていく様は過去の記憶をだんだんと思い出していく Kay とプレイヤーを感覚的につなぐ役目を果たしていたように思える。
終始何をやっているのかわからなく感じた一番の要因は、そもそも Kay の対峙すべき課題というか究極的な目標は「家族との再会」なのかどうかがずっと曖昧だったせいなのかもしれない。
結果的に母親が追っていた湖の底の謎の建造物や Superduck の問題がどうにもならなくなってしまい(というか半ば勝手に解決してしまい)、最終的に家族を連れ戻す以外の目的が消失してしまったように感じたのがちょっと面白かった。
なんか、こう、知らん間にチェックメイトされていたことに気づいて、「じゃあもうここしか進む場所ないじゃん」ってなったときの投げやりな解放感のようななにか。最初に望んだ形ではないにせよ堂々巡りの悩みから解消されたことには違いない。
グロテスクで巨大な鳥のような見た目をした Superduck は何かを象徴しているようでもあり土着信仰の偶像のようでもあるし、キマってる時に見た幻覚のようでもある。これは作品の全体的な雰囲気にもそのまま当てはまるような気がした。
意志や目的はなくただ拡大だけを続けるネットミームのような Superduck と、終末思想を煽るカルトの Garret たち、そして Norco を牛耳る巨大企業の Shield。これらが最終的に Stone を追いかけた結果自壊し、母親の研究が正しかったことの証明も完了した形になったのは気持ちの良い結末に見えるけど、実際は主人公が首を突っ込んだ問題はすべて、Norco がミシシッピ川に沈むのと同じように、ただ勝手に消滅していっただけ。そんな中でも諦観や無力感を受け入れるだけじゃない終わり方をしたのは良かった気がする。
特に、主人公たち(Catherene と Kay)の目的や利害と関係なく、明確に人のためとして行った Bruce のクエストを進めることで、最終的に家族とロケットから逃げ出すこができたというのは、終始ドライな雰囲気の中でも良心のようなものを感じた。
あと、不完全に再現された母親のAIと会話するシーンや、長年連れ添ったアンドロイドの Million が Shield のスパイだったことが判明するシーンでも、割とあっさり気味に処理されるのがなんとなく好きというか、なんだろう。
- 「南部ゴシック」を何にも知らなかったので、とりあえず Kindle にあったフォークナーの短編集『エミリーにバラを(中公文庫)』を読んだけど、完結で素朴な文体だけどどこか冗長で常に曖昧な感じが少し雰囲気似ているのかもしれないと思った。あと、ずっと代名詞だけで出てきて、はっきりと誰/何のことなのかが後々までわからない感じとか。ホントにこれだけ読んだ何もわからないし、そもそもこういう文学のジャンルってだれがどうやって決めてるの?なんかえらい教授とかがきめてたりするの?
- インタビュー記事によると、作者は地元のルイジアナ州ノルコとミッドガルに共通点を見出していたらしい。FF7もやらなくちゃいけないのか。
- インタビューではスラヴォイ・ジジェクやマイク・デイヴィスに影響を受けたとはっきりと言っているし(このゲームじゃなくて作者の個人的な話ではあるけど)、なんかもう一個深い意味とか象徴的ななんかがありそうなんだけど、知識が浅くてそういうのわかってない感じがある。
- 開発者が作成した参考文献や設定資料が参照できるソフトがあって、そこで Stone のモチーフについての説明もあった。あえて曖昧にしてあるところにわざわざ答えを見に行くのはあれっちゃあれかもしれないけど面白かった。設定資料はゲーム中に説明されている内容からそれほど予想不可能なものではないけど、参考文献として挙げられているものは理解に役立った。